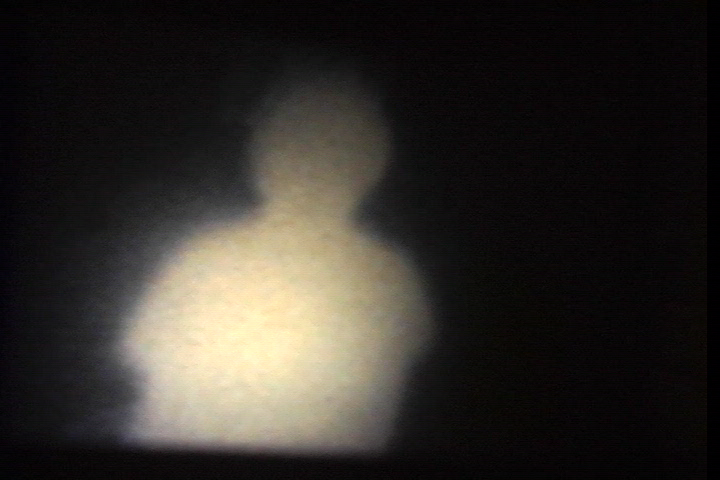『きおく きろく いま』『いぬごやのぼうけん』公開記念・水本博之監督インタビュー
(全4回 / 聞き手・構成 若木康輔 / 2017年収録)
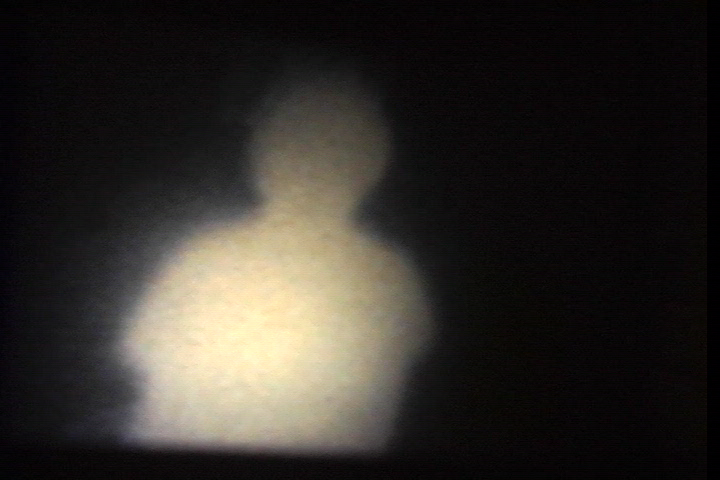
『2つの旅とコーヒー』より ©Belumg Belumg Na Uai
第3回 初期作品について
水本さんは2本の長編ドキュメンタリーと『きおく きろく いま』『いぬごやのぼうけん』に至るまでに、『2つの旅とコーヒー』(2005)、『深海から来る音』(2006/PFFアワード入選)、『舞いあがる塩』(2007/PFFアワード入選)、『買物袋と馬の親子』(2008)、『気球α号の墜落』(2010)といった作品を発表しています。
公開作の参考になると思う点を伺いますが、初期のユニークな特徴は、怪獣がよく出てくるところ。
「怪獣映画の存在は、大学にいた時は強く意識していました」
怪獣は、『2つの旅とコーヒー』では「都市の記憶を破壊するもの」として説明され、『深海から来る音』では、海の底、人知の及ばぬ世界から現れる。日本の怪獣映画の約束事に則りつつ、より思弁的です。『シン・ゴジラ』(16)よりも深く怪獣を理解しているのではないか、とさえ。
「あまり大きなことは言えないですけど……。あの映画に言いたいことは一杯あります(笑)。
いずれにせよ若かった頃の、分かりにくいものを作っていた時代ですね」
水本さんの初期の“怪獣映画”にも、子どもにダイレクトに伝わるところがあると思いますよ。僕らだって、例えば『ウルトラセブン』の「ノンマルトの使者」(68)を再放送で初めて見た時、妙に怖かったり哀しかったりしたでしょう。しかも水本さんは、ファンが好きで作った範疇を越えて、自分の中の内面にまで落とし込んでいる。怪獣には文明懐疑の暗喩が常に付きまとう、というテーゼを深く理解した上で。
それは『繩文号とパクール号の航海』の終盤まで通じます。大洋を小さな舟で渡ったインドネシアの漁民たちが、日本に辿り着いたあと、何に喜ぶかといえば、新幹線に乗ることだった。あの場面をあえて水本さんが用意したことで、観る人は海洋の冒険を楽しむ世界からこぼれた、静かなショックを受け取ることになる。

『縄文号とパクール号の航海』より ©Yohei SATO
「怪獣映画の影響をしばらくは忘れていたんですが、最近になって実は今の自分とつながっているなと。日本の怪獣映画には、南方というキーワードがありますよね。『繩文号とパクール号の航海』はまさにそういう映画です。南方から我々とは違う文明が海を越えてやってくる。そういう構造を組み立てている時には、思考のベースに『モスラ』(61)は確実にありました」
「怪獣は、内的な破壊衝動の象徴でもあります。ビル街を踏み潰す姿に見る人は破壊の快楽を仮託し、カタルシスを得る。一方で怪獣は妖怪の一種でもありますよね。共同体が背負ってしまう業としての存在。そういったことは、昔から考えていました」
「それでも、『2つの旅とコーヒー』を作ったのは大学生の時。社会のことをぜんぜん分かっていないわけです。なんとなく不安に思っていることを表現しただけで、そこまで具体性が無かった。外の世界、他者と出会うことでようやくいろいろなことが分かってきました。肩書や金銭と、具体的にメシを噛んで飲み込んで消化して生きる活動との対比を考えるうち、社会が見えてきた。世の中に対してそれは違うんじゃないか、と思うことも出てきますし、そこまで考えてやっと表現が出来る。当時は分からなかったので、怪獣の存在もいささかボンヤリしていたと思います」
文明破壊のカタルシスは、畏れと表裏一体ではある。怪獣が現れるかもしれない、という気配づくりがとても上手いです。海辺での釣りがそれを象徴している。釣り糸の下に、確かに見えないものがいる。そことの連絡の具象になっている。大体、水本さんの作品には、全てを通じて釣りをする場面が多い。
「ああ。それは、初めて気づきました(笑)。別に釣りが好きなわけでもないんですが……おそらく、海辺に人がいる時の、絵の問題だと思います。食べるために魚を釣る、その姿は生産活動の象徴として端的でしょう?」
なるほど。一方で、『深海から来る音』は若い連中が釣り糸を垂らしていると、赤いお面の深海人?が現れ、『いぬごやのぼうけん』も、釣り糸を垂らしていると大きなトラブルがやってくる。畏れのライトモチーフとしても、つながっているんですよね。
「水面という境界線があるじゃないですか。我々と海の間に。『繩文号とパクール号の航海』はずっとその上を走る映画ではありました」
あれこそマンダール人が釣りをしまくる、一大フィッシング映画。
「水面の下に見えない世界、人間の及ばぬ世界があるというのは、まさにその通りだと思います。マンダール人はあんまり泳がないんですよ。海水の中に身体を入れるのを怖がるんです」

『縄文号とパクール号の航海』より ©Yohei SATO
僕が初めて見た水本作品は『繩文号とパクール号の航海』ですが、文明とは何かということを、よく考えている人だなと。なので、ますます初期作品の怪獣とのつながりが納得いった。
「学生時代、『ウルトラ』シリーズの脚本を書いた佐々木守さんが大学に来ていたんですよ。僕は佐々木さんに対して、他の学生よりも強い憧れを持っていましたけど、シナリオを書く技術も無かったので、授業は受けたけど教えを直接乞うまではいきませんでした。遠巻きに見ている感じで」
「子どもの頃から怪獣ものを見ていたけれど、改めて大人になってから見直して、どんなテーマが含まれているかについてはずっと考えていたんです。だから、自分が映画を作るからには怪獣が出てくるものという考えは当初からありましたし、怪獣が出るからには物語の上でなぜ出て来るのか、意味は重要だと思っていました。意味といっても、生物学的なそれではなくて」

『深海から来る音』より ©Belumg Belumg Na Uai
こういう初期作品があった上で、ドキュメンタリーに行く。知らない人、知らない土地と出会う経験をしたくなる。そういう水本さんのあり方は、お話を聞くと理解できます。
「初期作品はずっと自分の中で机上の空論を繰り返していた、というところがあります。今も描きたいこと、言いたいことの基本は『2つの旅とコーヒー』と全く同じなんですけど。インドネシアに取材に行って経験を積んでようやく、描きたいことに具体的な力が付いたなと感じています」
「つまり当時の僕は、どこか中二病っぽかったわけです(笑)。都市論、文明論のモノローグにしても、こんな大きなことを自分が言っていいのかな、と不安に思いながらでした。知識や経験が追いついていないのは分かっていたし。映画の中で言っていることは間違いないと思いつつ、自分自身に対して自信を持てない、誇れない気持ちがあって。
だから、ドキュメンタリーに関わるようになり、現実の中に深く身を置いて情報を掴めるようになったのは大きいです。抽象的なイメージが先行していたことを、自分の目で見てきた経験の上で語り直せるようになりましたから」
『2つの旅とコーヒー』では、原っぱから現れた怪獣が何も災厄を起こすことなくまた藪の中に消えてしまいます。それを目撃した〈自分〉も、結局は幽霊のひとりに過ぎないのだと内省のモノローグをつぶやくことになる。そこの理屈は確かに頭でっかちな気はするのですが、『2つの旅とコーヒー』の2部では、風が吹いて消えようが、何度でも砂の上に字を書き続けるという挿話が出てきます。その都度、水本さんは自分の心境を正直に映画に描き込んでいますね。ほんとにこれでいいのか、という問い掛けを自分にしながらだから、作品歴自体がひとつの旅の跡と見える。
「はい。だから、だんだん苦しくなったんだと言えます。転機のきっかけとなったのは、『買物袋と馬の親子』です。友達の結婚式用に作ったアニメーションで、これが、映画に興味の無い人にも見てもらうことを意識した最初の作品なんです」

『買物袋と馬の親子』より ©Belumg Belumg Na Uai
でも、僕は実は『買物袋と馬の親子』が一番難解だった。ネギが飛び出しているビニールの買い物袋を馬に渡すって、どういうことだろう(笑)。村の美術は、アルメニアかどこかのように抽象的に作られていて、そこに突然、日本の日常と直結したビニール袋が出てくる。
「そこは……直観です(笑)。作っている時は、深く考えていないんですよね」
『気球α号の墜落』は、架空の壁を気球で乗り越える寓話と、実写で若者の気分を淡々と描く日常リアリズムが並行していて、また新たな切り口を模索しています。
「あくまで自分の描きたいことは同じでしたが。自分の半径30メートルの日常と、社会という漠然としたイメージとの断層を描きたかったのかな。
映画が始まった時、主人公達は2つの世界を接着できていないし、社会のディティールも分かっていない状態でいます。その中で自分の半径30メートルを移動させ、友人達とつながり、自分の時間を生きようとすると外部の世界に多少の影響が出るのか、あるいは出ないのかを考えていたのだと思います。
でも、いまを生きる多くの若い人が社会の中で働くなかで、誰もが自分の実感を持って接着できているかというと、そうではない気がしますし」
「自分がどういう世界に生きているか。なぜここにいるのか。自分の知らない違う世界があるのではないか。空想の物語を作るとしても、そういうことを考える必要があるといつも思っていました。地続きの暮らしの中で、想念をちゃんと接着させたいともがいていた時期の映画だと思います」
水本さんの年齢の頃の大学生は、大変だったろうなという気はします。〈終わりなき日常〉という言葉が盛んに言われていた、ある大きな澱みを経験せざるを得なかったところがあるのでは。世の中がこのままでいいとはとても思えないけど、どう折り合っていくべきか分からない、というような……。映画で言うと、黒沢清監督作品の持つ気配のあり方がヴィヴィッドだった時期でもある。
「僕は、特に『回路』(01)が好きでした」
2011年の東日本大震災は? あそこで、物事がクリアになったという変化は確かにあった気がするんです。世の中を真面目に考えることに対して、特に何かフィルターを準備する必要が無くなった。
「はい。自分と世界が繋がっている実感を得られやすくなった面はあるかもしれません。映画にしろ何にしろ、自分が行動を起こすことに意味があると感じられる人は多くいたと思います」
こんな世界であってほしい、と個人が言いやすくなったとは思うんです。2010年までの数年間と比べたら。
「『気球α号の墜落』を作っていた頃は僕も煮詰まっていたけど、おそらく他の人も煮詰まっていた。この後に作り、封印している作品では残酷な描写を沢山しているんです。ゼロ年代の後半は、そういう描写は徹底的にやったほうが真摯である、と考える人が多かった。それで僕も約1年かけて作ったんですけど、やってみて、ああ、そうじゃないな。これではいかんな、と分かったんです。残酷描写に殉じるほどの覚悟があればいいんですけど。僕はそこまでは持てないし、自分はそうじゃないと分かった」
(第4回 作家としての資質とこれから に続く)
【話し手】
水本博之(みずもと・ひろゆき)
1982年生まれ。グレートジャーニーで知られる探検家・ 関野吉晴の手づくりカヌーの旅に同行しドキュメンタリー映画『縄文号とパクール号の航海』(2015) を監督。以後もドキュメンタリーを制作中。一方で手づくりにこだわった人形アニメーションも制作、国内外で発表している。
【聞き手・構成】
若木康輔(わかき・こうすけ)
1968年北海道生まれ。日本映画学校卒。1996年よりフリーランスの構成作家。2006年頃より映画ライターとしても活動。ドキュメンタリー・レコードの廃盤を紹介する「ワカキコースケのDIG!聴くメンタリー」をneoneoウェブで連載中。