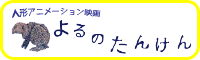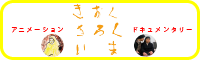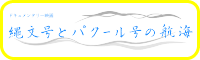『きおく きろく いま』『いぬごやのぼうけん』公開記念・水本博之監督インタビュー
(全4回 / 聞き手・構成 若木康輔 / 2017年収録)

『いぬごやのぼうけん』より ©Belumg Belumg Na Uai
第1回 『いぬごやのぼうけん』
水本博之さんは、ドキュメンタリー映画『僕らのカヌーができるまで』(10年公開・共同監督)と『繩文号とパクール号の航海』(15年公開)の2本で世に名を出した人ですが、実はそれ以前から人形アニメーションを個人で制作する、アニメーション作家でもあります。実験的なドキュメンタリー『きおく きろく いま』(15)と童話的なアニメーション『いぬごやのぼうけん』(11)の、今年(17年)の下北沢トリウッドでの同時公開は、水本さんのユニークな作家性を知ってもらう良い機会となると思います。
「もう1本、もうじき完成する予定のアニメーションがあります。当初はその3本での上映を考えていたのですが、トリウッドの支配人に相談したところ、『今ある2本で、8月9日に向けてやろう。新作はまたいつでも出来るよ』と提案されて。そこで、この2本での公開を決めました」
(注-『きおく きろく いま』は、1945年8月9日の長崎原爆投下が重要なモチーフに)
「『いぬごやのぼうけん』は、2009年に制作を始めました。『僕らのカヌーができるまで』が編集中で、ほぼ出来上がりつつある頃です」
このインタビューでは後で初期作品についても伺いますが、それらと比べると、『いぬごやのぼうけん』は起承転結がある構成も含めて、おはなしを作る意識が大きく前に出ています。ドキュメンタリーを並行して作った経験は関係ありますか。
「初期の作品にも一応のストーリーはあるのですが、確かに、呑み込みやすい意味での起承転結などは明確にはありませんでした。
『僕らのカヌーができるまで』は劇場公開されることが決まっていたので、この映画で初めて、一般のお客さんを相手にすることを考えました。
それまでは主に一人で分かりにくい作品を作っていて、その時は、それはそれでいいと思ってやっていたんですが(笑)、ふだん映画や表現に関わっていない人に見せなくてはいけなくなった時に、ああ、これじゃいかんなと思って。一度ちゃんと、子どもに見せられるものを作ってみようと。それが『いぬごやのぼうけん』です」
「その前に1本、エグいストーリーものを作っていたのですが、今は封印しています。そういうマニア向けみたいなものばかり作っているのは、いかんと思ってきたんです。いかんというか、そればっかりなのはどうかと。 そういう作品は理屈というか……結局、仲間内への訴求になってしまってどこか弱いんですね。映画が好きな人たちの間だけで作って見せているうちに、どんぐりの背比べになるというか。ふつうに暮らしている人たちと乖離した場にずっといるのは不毛だなと」
「子ども向けのアニメーションは、子どもが何かを感じてくれ、面白いと思ってくれたら、それが真実だから。大人に評価してもらうことはもちろん大切ですけど、そこにはその人の、それまでに受けてきた教育や知識などのバックボーンがあるでしょう。時には、人間関係が絡み合っている場合もあるし。だからその評価が果たして正しいのか、分からなくなったりするんです」
「そこで、これまでに作ってきた作品とはかなり大幅に舵を切り、誰に向けて作るのかの指向性を変えました。それが『いぬごやのぼうけん』です。
もちろん、子どもに受けるためにめざといことをするつもりは無くて。受けりゃいいってわけじゃない。甘いお菓子を口元まで運んであげるような表現はしたくないのが前提です」

『いぬごやのぼうけん』より ©Belumg Belumg Na Uai
『いぬごやのぼうけん』は、大雨が洪水になり、少年と犬が犬小屋ごと海に流されて旅をする話。時期はこちらのほうが先だと思いますが、取材が始まっていた『繩文号とパクール号の航海』でも東日本大震災を経験し、マンダール人が乗り込んでいた舟のキャプテンを水難事故で失っている。
「そうですね。僕らは6年前、大津波が来て、町全体が波の下になるところを見てしまった」
「『繩文号とパクール号の航海』の終盤のある場面は、僕にとって大事です。亡くなったキャプテンの歌声が海から聞こえてくる場面です。あそこは、エコーと共に海面にキャプテンの歌声が浮かび上がってくる、そう感じ取れるように意図的に作っているんです。死者が戻ってきて、生きて目的地に向かうクルーの背中を押してくれていると表現したかった」
「『いぬごやのぼうけん』でも、少年が釣り糸を垂らしている海の下に、海底に沈んだ戦車を描いているんです。当時は無意識に添えたのですが、過去との連結、地獄との連結……そういう考えはあったのかもしれません」

『縄文号とパクール号の航海』より ©Yohei SATO

『縄文号とパクール号の航海』より ©Hiroyuki MIZUMOTO
大雨は町を呑み込むが、カタストロフィではなく、少年と犬の冒険の始まりである。そこに、水本さんの願望があるのかな。
「うーん……何でだろう(笑)」
水本さんの作品のライトモチーフには、もう一つ、旅がある。旅と水。その点では『いぬごやのぼうけん』は、『繩文号とパクール号の航海』と同じぐらい、水本さんのエッセンスが凝縮されたものになっています。
「自然とそうなっていますね。『僕らのカヌーができるまで』は、舟が出来るまでの映画なんですよ。あの作品では僕はインドネシアまで行っていなくて、実際には現地で舟を見ていない。その後も撮影に関わることは無いだろうと思っていたので、その続き、舟が旅をする空想イメージが頭の中で生まれていたんです」
「なぜ洪水かというと、僕がそういう夢を見たんです。夢で見て、目を覚ました後も覚えている風景を描くことが多いです。『いぬごやのぼうけん』も、波の上に屋根だけが浮かび、その上に人がいる映像があった。 ただ、洪水を洪水として描くと収拾がつかなくなるし、悲劇になってしまうので。それで、子どもと犬だけが海に運ばれ、冒険をする話にしたんです。子ども向けを意識して作っていますから。どこかでファンタジーにしよう、という判断の切り替えはありましたね」
しかし、せっかくの冒険なのに、大きなカニの怪獣を前にして少年と犬は成す術もない。徹底して無力ですよね。
「制作当時の心境かと思います。僕自身が何か出来るという手応えが薄く、自信に満ち溢れる状態ではなかった。でもそのなかで、つまらないことが沢山起きても、それはそれで、と飄々と受け流して日々を楽しくやっていきたいし、むしろそれが価値なんじゃないかと考えていたんです」
「何かに立ち向かい、勝利を得ようとする人たちとは違う……勝利するとはつまり、いずれ敗北も付きまとうわけですからね。勝利に価値を見出す人は、いつか敗北してしまいます。今その瞬間を生きて、目の前の人と仲良くする、小さな出来事に喜びを見出すことのほうが大事なんじゃないか」

『いぬごやのぼうけん』より ©Belumg Belumg Na Uai
「この時期、本当に僕は苦しい時期でした。生活的にも、精神的にも、創作者としても。それまで、人に見せてもハテナという顔をされる作品しか作ってきていないというのは、自分の弱点だと思わざるを得なかった。そういう感情は全て、『いぬごやのぼうけん』に流れ込んでいると思います」
「要は、技術開発から何から、一人でしているわけですからね。アニメーションの撮影台の作り方を誰かに教わったわけじゃないし。一から自分で組んで、美術も全部自分で作って」
海の遠近感など、よく手作りで会得しましたね。
「効率を優先したら絶対に許されないことばかりやっているんですよ。ハンドルで高さを調整できる良い撮影台を使って、ユーリ・ノルシュテインのように存分に作りたい気持ちは凄くあるんですけど」
「美術も、粘土などホームセンターで手に入るものでしか作っていませんからね。夜の海に浮かぶビル群も、すべて段ボールです。
昔、ジオラマを作っていた時期はあったんです。その時にある程度、工夫する方法を学びました。例えば粘土を買うお金も無くなった時は、ボンドにちぎったトイレットペーパーを混ぜていけば、山のようなものを作れるんですよね。今ならもっと良いものを作れますよ(笑)。
そうやって一つずつなので、アニメーションはある日突然出来る、ということは無いんです」
(第2回 『きおく きろく いま』に続く)
【話し手】
水本博之(みずもと・ひろゆき)
1982年生まれ。グレートジャーニーで知られる探検家・ 関野吉晴の手づくりカヌーの旅に同行しドキュメンタリー映画『縄文号とパクール号の航海』(2015) を監督。以後もドキュメンタリーを制作中。一方で手づくりにこだわった人形アニメーションも制作、国内外で発表している。
【聞き手・構成】
若木康輔(わかき・こうすけ)
1968年北海道生まれ。日本映画学校卒。1996年よりフリーランスの構成作家。2006年頃より映画ライターとしても活動。ドキュメンタリー・レコードの廃盤を紹介する「ワカキコースケのDIG!聴くメンタリー」をneoneoウェブで連載中。
*本ページの画像の無断転用・転載を禁じます